
ここは夢園荘
唯菜の章
「はい……大丈夫ですから。ご飯もきちんと食べてますし、夢園荘の皆さんにもよくして貰ってますから……はい……では、また電話します。それでは……」
”カチャン……。”
電話を切ると、受話器に手を置いたまま溜め息をついた。
「もういい加減にして欲しいです……」
私の名前は葛城唯菜。17歳、高校1年生。
年齢があわないとお思いだと思いますが、実は去年重い病気を患って丸1年休学をしていたんです。
それでも2月に全快、3月に退院をして4月から復学。1年も休んでいたわけですから進級できるわけもないので1年生をしています。
当然と言えば当然ですね(^^)
そして私は9月からこの夢園荘302号室で1人暮らしをはじめました。
なぜ9月からかというと、夏休み前までは自宅から学校に通っていたのですが、片道2時間のバスと電車を利用した通学。
元気になったとは言え、病み上がりの私にはそれは辛いことに変わりなく、さらに痴漢はでるし最悪。
というわけで学校の近く(歩いて30分)にあるこの夢園荘に入居することになりました。
問題だったのは心配性の両親の説得でしたが、三日ほど天の岩戸をしたら泣く泣く許可してくれました。
普段おとなしくしてるから驚いたかも知れませんね(^^)
でも許可してくれたまでは良かったのですが、『1日1回電話すること』『週末は家に帰ってくること』の2点を義務づけられてしまいました。
私のことを心配してくれるのは嬉しいけど、すっっっっごく過保護すぎると思いませんか?
「はぁ……」
思わず深い溜め息。
”コンコン”
「はい?」
ドアを開けるとお隣の樋山恵理さんがいた。
「やっほ〜!」
いつも明るい人ですね……この人は……。というか悩みとは無縁のような……。
「暗いね……私もしかしたら迷惑だった?」
「いえ、そう言うわけではないんですが……恵理さんっていつも悩みが無さそうで羨ましいなぁって……」
「ひどいこと考えてるなぁ……私だってちゃ〜〜んと悩み事あるんだぞ」
「そうなんですか?」
「そうだよ。私だって恋で悩んでいるだぞ」
恵理さんは口をとがらして私に抗議する。
私は彼女のこういうところがなんか可愛い人だと思ってしまいます。
「もう可愛いだなんて照れちゃうな」
問題は時々人の心を読みます(^^;;
管理人さん曰く、恵理さんは読心術を心得ているそうですが、そう言う問題でしょうか?
「それで私に恋の相談をしに来たと……」
「じゃなくて……相変わらず冷静にぼけるね(^^;」
「はぁ……」
「さっき実家から戻ってきたんでしょ。だ・か・ら」
「お土産ですか?」
「そう、それ!」
恵理さんは自分が考えてることが、私に伝わったことが嬉しいらしくはしゃいでる感じ。
でも彼女のこういうところが私は好きなのかも知れません。
私は思わず笑みをこぼしました。
「何笑ってるの?」
恵理さんは不満そうに言う。
「何でもありません、ただの思い出し笑いです。恵理さん、ここで立ち話もなんですから中に入りませんか?」
「うん、入る入るぅ。……あれ?」
「どうしました?」
動きを止めた恵理さんの視線を追いかけると、ちょうど階段を上ってきた榊由恵さんの姿。
由恵さんは私の部屋を挟んで恵理さんの反対側の303号室に住んでいます。
「ゆ〜えちゃ〜〜ん、今帰ってきたところ?」
「うん。しっかし、陸上部は上がりが早くて良いよね。水泳部なんてなんだかんだでこんな時間だもん」
「ぼやかない、ぼやかない」
「え〜り〜〜。……唯菜は何で困った顔してるのかな?」
「私帰宅部だから……なんと言って良いのか分からなくて……」
「人それぞれ好きなことやってるからそれで良いんじゃない?」
「一番好きなことやってる恵理に言われたらお終いだな」
「どう言う意味?」
「そう言う意味」
「う〜〜〜〜」
「がるるるぅ」
「「わん」」
私達3人は偶然にも同じ高校で、しかも恵理さんと由恵さんは同じクラスなんだそうです。
病気で休学してなければもしかしたら私も同じクラスになれたかも(^^)
それで由恵さんも私と同じ夏休み明けにここに入居したんですが、由恵さんの場合ずっと1人暮らしをしたかったんですが、今まで良いアパートが見つからずにいた時に恵理さんがこの夢園荘を紹介したそうなんです。
「ところで二人してここで何やってるの?」
「唯菜ちゃんのお土産を頂こうとしてるところ」
「恵理……あんたって……」
「なによぉ。自分の気持ちの正直に行動してるだけじゃない」
「唯菜も大変だね」
「私はいいんですよ。それに楽しいですから」
「ほらぁ、唯菜も良いって言ってることだし、由恵も一緒に頂こうよ」
「あんたには遠慮という物がないのか」
「……」
そこで急に恵理さんは黙り、じっと由恵さんを見つめる。
「な、なによ」
「唯菜、由恵はいらないって。二人で仲良く分けましょ」
恵理さんが私を後ろから押して中に入ろうとする。
「え、でも……」
「いいのいいのぉ」
「ちょっと恵理、いらないないんて誰も言ってないでしょ!」
「あれぇ、そうなのぉ」
「あんてって娘は」
あ……握り拳をふるわせてる……。
それでこちらは……口笛ふきながらごまかしてる……。
「くす……ふふふふふふ……あははははは……」
私は思わず笑い出してしまった。
「ほら恵理のせいで、唯菜に笑われたじゃない」
「なんで私のせいにするかなぁ……。でも良いんじゃないの。笑ってる方がさ」
今、恵理さんは何て……?
「今なんて言ったの?」
「独り言」
「恵理さん……」
もしかして私のために……それは考え過ぎかな……。
「ほ〜ら、な〜に暗い顔してるの。早くお土産食べましょ」
「恵理さん……もしかしてお土産が食べ物って決めつけてるんですか?」
「え……違うの……」
「そ、そんな……」
「由恵さんまで(^^;; お二人とも大丈夫ですよ。お饅頭と母が作ってくれた煮物ですから」
「「よっし!」」
パン、パン、パン、ガシッ!
互いに手をたたき合って喜びの表現。
本当に羨ましいぐらい仲の良い二人。
そんなほほえましい光景の後、私は二人に押されるように部屋の中に入ると、そのまま夕飯となりました。
「さてと……」
夕飯も済み、3人で他愛もない話で盛り上がっていると突然、由恵さんが立ち上がった。
「由恵、何処に行くの? もしかしてトイレ?」
「違うって、宿題やらなきゃいけないでしょ」
「宿題?」
「そう、明日までのがあったでしょ」
「……ああ」
恵理さんはまるで思い出したようにポンと手を叩いた。
「それなら出た直後の休み時間中に終わらせた」
「……そういえば、あんたっていつもそうだよね……見せて」
「ヤダ」
「即答かい!」
「うん」
「あんたを頼ろうとした私がバカだった。じゃ、私先に戻るね。唯菜、ごちそうさま」
「いえ、お粗末様でした」
由恵さんは力無くと言うかやれやれと言った様子で部屋を出ていった。
「良いんですか?」
「何が?」
「いえ、だから……」
「宿題は自分でやらないとね。答え合わせぐらいだったら見せても構わないけど、丸写しって言うのはちょっとね……」
「まじめ……なんですね」
ちょっち意外な素顔。
「違うよ。自分が苦労してやったのを楽しようとする他人に見せるのが嫌なだけ」
前言撤回、やっぱり恵理さんでした。
「ねぇ唯菜……」
恵理さんは先ほどまでの冗談ばかり言っていた表情とはうってかわって凄くまじめな顔で私の顔を見る。
「何ですか?」
「心配してくれる人がいるってことはそれだけで幸せなんだよ」
「恵理さん……」
「あなたはそれを嫌がってるみたいだけどね」
「……………」
私は恵理さんから目をそらした。
「私には心配してくれる両親がもういないから……唯菜のこと羨ましいんだ」
両親が……いない?
「私が小学生の時に事故で亡くなってね。そのからは親戚中たらい回し。最後に行き着いた場所がここなの。ホント、夏樹さんの両親に出会わなかったら今頃どうなっていたことか……」
恵理さんは笑って言う。
でもその目は笑っていない。
「でもこのこと夏樹さんは知らないから内緒の話」
「どうして……」
「ん?」
「どうしてそんな話を私に……」
「どうしてかなぁ……自分でも分からないや。でも一つ言えることは、両親の心配を嫌がらずに受け入れてあげないと」
「だけど……」
「そのうえで、これでもかってぐらい心配かけさせちゃえば良いと思うよ」
「え……」
両親を大切にしなさいとか言われると思ったのに、全く予想外の言葉……。
「そういうもんだよ」
「そうなんですか?」
「そうそう(^^)」
「でもそんな親不孝みたいなまねして……」
「私ね、最高の親孝行って親よりも先に死なないことだと思ってるんだ」
「……」
「さっきも言ったとおり私には孝行したくても親がいないから……だからそう言う風に考えてるの。だってそうじゃないと辛いし……」
「恵理さん……」
「でもね決して親の分まで生きようとは思ってないよ。私の命は私の物なんだから。それでも両親がくれた命だから大切にしようって思ってる。同時に自分の思ったとおり精一杯やっていこうって決めてるんだ」
私は何も言えなくなってしまった。
恵理さんは小さいときに両親を亡くして、親戚をたらい回しにされて、どうしてここまで強く生きることが出来るんだろう。
「ちょっと話がそれちゃったかな? とにかく自分の思った通りにやっていった方が良いよと言う話」
最後は明るく締めた。
「ああ、そんな暗い顔しないでよぉ」
「だけど私……」
「自分をしっかり持って、自分の思った通りに、しっかりと前を向いて歩く。たった17年しか生きてないけど、その17年間で私が学んだこと」
恵理さんの私に向けるその笑顔は凄くまぶしかった。
「でもまぁ、私の言葉を鵜呑みにされても困るし、同情もいらないからね。あなたの人生はあなたの物なんだから、あなた自身でどうすればいいのか決めればいいわけ」
「でもいきなり決めろと言われても……」
「この場でパッと答えが出るなら誰も苦労なんてしないよ。時間はこれからまだまだたくさんあるんだし、ゆっくり考えれば良いんじゃないの」
今の瞬間、心の中のもやが晴れたような気がした。
そして私は笑顔で「はい」と答えた。
「そうそう、その笑顔を忘れないでね。あっともうこんな時間なんだ……ごめんね、遅くまで」
恵理さんは立ち上がりながらそう言う。
時間は日が変わろうとしていた。
「そんなこと無いです」
玄関まで恵理さんを見送る。
「さっきの話、他のみんなには内緒にしててね。同情されたくないから」
「はい?」
「何でもない何でもない。とにかく内緒ね」
「はい。……あの一つだけ聞かせてください」
「?」
「どうして私に話してくれたんですか?」
その問いに恵理さんはちょっと困ったような照れたような表情になった。
「私ね、笑顔の素敵な娘って好きだから。それだけだよ」
「?」
「さっきの笑顔ね、初めてあったときの笑顔だったよ」
「恵理さん……」
「それじゃ、お休み」
「お休みなさい」
”バタン”
ドアが閉まると同時に部屋に静けさが戻ります。
でも今はこの静けさは嫌じゃないかも知れません。
恵理さんの強さを感じたから……。
私もこれから恵理さんに負けないように頑張りたいと思います。
きっとそれが私を励ましくれた恵理さんへの唯一の恩返しになると思うから……。
「唯菜、ファイト!」
<あとがき>
恵理「ううううう、なんて私ってば不幸な生い立ちなんでしょう(;_;)」
絵夢「どうしたの?」
恵理「マスター!、私は幸せになれますよね!!」
絵夢「私って『ここは〜』の?」
恵理「そうです」
絵夢「どうだろう。一応最終回まで考えてあるけどね」
恵理「幸せにしなかったら呪ってやるぅぅ(;_;)」
ダダダダダダダダダダダダダダダダ………(恵理、泣きながらどこかに走っていく)
絵夢「(^^;; そう言うわけで次回もお楽しみ」

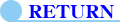
![]()
![]()