
ここは夢園荘AfterStory
Fragment Age
第二十三話 <まなみ IV>
夢。
昔の夢。
思い出の夢。
夏樹お兄ちゃんからお母さんが倒れたと聞き、すぐに駆けつけるとそこにはベッドに横たわるお母さんの姿があった。
「あ……あ……」
信じられない気持ちでいっぱいだった。
朝もいつものように出て行ったのに、それがこんな事になるなんて……。
私はベッドの側に寄ると掛け布団を掴んだ。
「ねぇ、起きてよ。ねぇねぇ……起きてよぉ。私……私……ねぇ……ねぇってばぁ」
何度も身体を揺するが起きる気配はなかった。
もしかしたら2度と目を覚まさないんじゃないかという恐怖が私を襲う。
「お願いだから……もうやだよぉ。お願い……起きて……」
堪えきれず涙を流す。
それでも起こそうと身体を揺する。
そして私の口から今まで言いたくても言えなかった言葉が出た。
「お母さん!」
その後は堰を切ったように何度も「お母さん」と呼び続けた。
今まで言えなかったのが不思議なぐらいに……。
するとお母さんはゆっくりと目を覚まし、私の頬に手を触れた。
「お母さん……」
「まなみ……『お母さん』って呼んでくれたの?」
私はこくんと頷き、「お母さん!」と呼びながらその胸に抱き付いた。
そしてお母さんも身体を起こし私を抱きしめてくれた。
私の名前を何度も呼びながら……。
でもその後のことは良く覚えてない。
ただ、私は夏樹お兄ちゃんに騙されたと言うことだけは分かった。
結果を見れば良かったんだけど、でも騙したことが許せなくてしばらく口をきいてあげなかった。
その時の夏樹お兄ちゃんの困った顔は面白かったな。
小学校6年の冬休み間近のある日、朝食の準備をしている私にお母さんが何か奥歯に物が詰まったような言い方で私を呼んだ。
「どうしたの?」
私は手を止めずに聞く。
「あの……あのね」
「うん」
「あの……」
「お母さん」
「はい」
「言いたいことがあるなら早く言って。私だって忙しいんだからね」
「うん、ごめんね。そのね、椿君って覚えてるかな?」
「椿さん? 知ってるよ。良くお母さんと一緒に仕事してる人でしょ。その人がどうかしたの?」
「実はね……あの……その……」
「お母さん、言いたいことははっきり言って」
私はフライパンから目玉焼きをテーブルに並べられたお皿に移しながら言う。
「えっとそのプロポーズされたの」
「声が小さくて聞こえなかったんだけど」
「だからプロポーズされたの!」
お母さんはそう言うと顔を赤くして俯いた。
「……でもね、まなみが嫌なら断るつもりでいるの」
「良いんじゃない?」
冷蔵庫から作り置きのサラダを出しながら答えた。
「え?」
でもお母さんは私の返事を意外だと思ったのかきょとんとした顔をしている。
「だから私は良いと思うよ」
お母さんの向かいの席に座りトースターにパンを入れながら言う。
「本当に良いの、まなみ?」
「良いも何も、反対する理由なんてないじゃない。椿さんのことは別に知らない訳じゃないしね。それよりもお母さんはどうなの?」
「私は……この通りおばちゃんだし、未亡人だし……」
「あのねぇ……大切なのはお母さんの気持ちでしょ。椿さんのこと嫌いなの?」
「嫌いじゃないよ。むしろ好き。仕事上のパートナー以上に……」
「だったら決まりでしょ」
もじもじしながら言うお母さんに苦笑を漏らしながら焼けたパンをトースターから取り出しそれぞれのお皿に置く。
「でも……まなみは本当に良いの?」
「くどい。私は良いって言ったはずだよ」
「うん……」
「もう、お母さんは早く朝ご飯食べて、会社に行って椿さんにOKの返事を言う。分かった?」
お母さんのじれったい態度に私は口早に少し強めに言うとお母さんは黙ってこくんと頷くと朝食に手を付け始めた。
その後はトントン調子に話が進み年明けに結婚する。
そこで私はあっちゃんと出会った。
最初の頃は私も女の子だと思ったというのは今でも言ってない。
式が終わってすぐに私達は今まで住んでいたアパートから出て大きなマンションに引っ越した。
そこで親子三人での新しい生活が始まった。
ちなみに椿さんの事を「お父さん」と簡単に呼ぶことが出来た。
そして、私が変わり始めたのはたぶんこの頃……。
それまで仕事で忙しいお母さんの代わりに私が家事の全てをやっていたのだけれど、結婚してからは家事のほとんどをお母さんがやるようになってしまった。
結婚してからそのまま働き続けてるんだけど、あまり残業をしないですむようになったことが理由みたい。
私としては簡単な手伝いだけですむようになって楽になったので良かった。
……初めのうちはそう思ってた。
でもだんだんと何か物足りないものを感じるようになった。
お母さんと暮らすようになってからずっとやってきた家事。
私にとって生活の一部になっていたこと。
時には嫌だと思っていたことではあったけど、それでも毎日が充実していた。
家事から解放されたことは、結果的に私の生活リズムの崩れを招き、生活に対する充実感の喪失に繋がった。
でもその時理由が分からなかった私は何か打ち込めば大丈夫だろうと思っていた。
だけど、何をやっても打ち込めることが出来ずに充実感を得ることが出来なかった。
それでも積極的に何でも参加するようにした。
でも何も得ることが出来ないまま時間だけが流れ、私の心の成長は止まった……いえ、無意識のうちに自分自身で止めたと言うのが正解なのかも知れない。
胸をもまれたりしてもただ痛いだけで『感じる』と言うことが無いことに気づいたのはそれから程なくだった。
それは中学の夏に父方の田舎に行ったときに再会したあっちゃんとホテルで一つになったときにはっきりした。
気づいたときには感情の出し方も忘れていた。
突然目の前が暗くなった。
まるで映画館の照明が落ちるかのように。
「まなみちゃん」
暗闇の中から誰かが私を呼ぶ。
「まなみちゃん」
再び声がする。
私はキョロキョロとあたりを見回し声の主を探した。
「こっちだよ」
その声に導かれるように振り向くとそこにはあっちゃんが立っていた。
「あっちゃん……良かった、無事だったんだ……」
あっちゃんは私に微笑みかけてくれる。
私はあっちゃんに近づきその身体に手を伸ばした。
そして触れた瞬間、あっちゃんの身体がまるでガラスのように砕け散った。
「え?」
私は目の前で何が起きたのか分からず、暫し呆然としその場に座り込む。
「あっちゃん? ねぇ……あっちゃん? あっちゃん、あっちゃん!」
足下に散らばるあっちゃんの破片をかき集めながら泣きながら名前を呼ぶ。
「あっちゃん、あっちゃん!、あっちゃん!!」
「あっちゃん!!!」
ハッと目を覚ますと天井の電灯の明かりが目に飛び込んできた。
「……夢?」
「目が覚めた?」
その声にちょっと頭を動かすと、葉月お姉ちゃんが優しい笑みで私の顔を見ている。
「葉月お姉ちゃん?」
自分が葉月お姉ちゃんの膝枕で長いすで横になっている事に気づいた。
「はい、ハンカチ」
葉月お姉ちゃんは持っていたハンカチを私に渡す。
「?」
「涙が零れてるよ。何か怖い夢を見たの?」
顔に手を当てると涙で頬が濡れていた。
「私…………、葉月お姉ちゃん、あっちゃんは!?」
私は身体を起こすと葉月お姉ちゃんに聞く。
「大丈夫よ。3時間ぐらい前に手術も終わって、今病室で寝ているわ」
その言葉を聞き、私は安堵の息を吐く。
でも次の瞬間、あっちゃんがこんな事になってしまった責任が自分にあることから、嬉しいのに喜ぶことができなかった。
「歩君は305号室よ、行かないの?」
「……行けないよ。あっちゃんがこんな事になったのは私のせいだから……」
椅子にちゃんと座り俯く私の足下が涙で濡れる。
「まなみ」
葉月お姉ちゃんは優しい声で私を呼ぶとそっと抱きしめてくれた。
「まなみは歩君のことどう想っているの?」
「……分からない。でも……」
「でも?」
「あっちゃんがいなくなると思うよすごく悲しかった。胸が苦しかった」
「そう。ずっと側にいて欲しい?」
「うん……たぶん……」
「そう。だったら大丈夫よ」
私は葉月お姉ちゃんの顔を見る。
「でも……でも……」
「歩君だってあなたのことを大切に想っているはずよ。あなたが今こうして無事でいることを知ったら歩君だって喜ぶはず。そうじゃない?」
「葉月……お姉ちゃん………」
その時、階段をにぎやかに駆け下りてくる足音が聞こえた。
振り向くと、睦月お姉ちゃんとしんさんの姿があった。
「あ、目を覚ましたんだ。歩君も目を覚ましたから呼びに来たの」
睦月お姉ちゃんは明るくそう言う。
でもそれに対して私の顔はまだ影を落としたままだと思う。
「ほら、まなみ。涙を拭いて歩君に会いに行きましょう」
そう言うと葉月お姉ちゃんはハンカチで私の頬を伝う涙を吹いてくれた。
そして葉月お姉ちゃんに背を押され立ち上がった。
「まなみ、行こうよ」
睦月お姉ちゃんは私の手を取り部屋へと連れて行こうとする。
でも怖くてその場から動けない……あっちゃんに会ってなんて言ったらいいのか分からない……。
「私……会えないよ……会いたいけど、会えないよぉ」
再び涙が零れる。
そんな私に睦月お姉ちゃんが優しく声をかけてくれた。
「あっちゃんもまなみに会いたがってるよ」
「え?」
「まなみが無事だと知ってすごく喜んでたよ」
「あっちゃんが……」
「だから行こう」
「まなみ、行きましょう」
葉月お姉ちゃんも私の手を取りそして歩き始める。
私は怖かったけど、でもそれに従いついて行った。
305号室と書かれた病室の前。
そこで私は足すくむ。
このドアの向こうにあっちゃんがいる。
でも……でも……。
「まなみ、早く」
睦月お姉ちゃんがドアをあけ中に連れ込まる。
「あっちゃん……」
ベッドの上で身体を起こしてこちらを見るあっちゃんの姿があった。
痛々しく頭に包帯を巻いている。
だけどその顔は嬉しそうな微笑みを私に向けてくれている。
「よかった、まなみちゃんが無事で」
その言葉と微笑みに私は再び涙を零す。
「あっちゃん……ごめんなさい」
「なんで謝るの?」
「だって私のせいであっちゃんが……」
「まなみちゃん、こっちに来て」
あっちゃんは私に手を差し伸べ、私を呼ぶ。
私は呼ばれるままにゆっくりと近づくと突然あっちゃんは私の腕を掴んで自分の方に引き寄せたと思ったらそのまま抱きしめられた。
一瞬何が起きたか分からずに目を丸くする。
「え?」
「まなみちゃんが無事で本当に良かった」
「あっちゃん……でも私のせいで……」
そこで私の口は何かに塞がれる。
すぐ目の前にあっちゃんの顔があることでそれがあっちゃんの唇だと言うことにすぐに気づいた。
どれぐらいの間そうしていたか分からない。
ゆっくりとあっちゃんの顔が離れていく。
「あ……あの……今……あの……」
「まなみちゃんがボクの事をどう思っているか分からないけど、ボクはまなみちゃんのことが好きだから……だから……えっと……」
私のことが好き? あっちゃんが私のことを? だからキス……。
混乱する私はどうして良いか分からず、今はあっちゃんの胸で泣いた。
この涙は悲しみの涙じゃなく、嬉し涙だと思うから……だから思いっきり泣いた。
<おまけ>
「恵理さん〜どうしたら……」
自分の胸で泣きじゃくるまなみに混乱する歩はドアの脇で立つ恵理に助けを求めた。
「良いんじゃないの、そのまま泣かせておけば。きっとそれは嬉し涙だよ」
「そ、そうなんですか?」
困惑する歩にドアの所に立つ睦月としんも茶々を入れる。
「歩君もやるね〜」
「うん、見直したぞ」
「二人まで〜〜〜」
文句を言うが恵理と睦月としんは笑いながらも二人を優しい目で見る。
「でもあそこでキスするなんてすごいね」
睦月が感心する。
「あ、それ、私の入れ知恵なの」
それに対して恵理が答える。
「まなみちゃんの状態も知ってたし、こういう時は何も言わずにキスした方が気持ちが伝わる物でしょ。私もそうだったし」
そう言いながら恵理は夏樹との事を思い出していた。
「と言うわけで歩君、まなみちゃん、おめでと〜」
恵理はウィンクしながら二人に祝福の言葉を贈る。
そして睦月としんもそれに続けて祝福の言葉を送った。
そんなにぎやかな中でもまなみはまだ歩の胸で泣き続けていた。
たぶん彼らの言葉は彼女には届いていないだろう。
<あとがき>
絵夢「さて、前回に引き続き、まなみと歩も決着しました」
恵理「でもまなみちゃんにあんな過去というか思いがあったなんて……」
絵夢「自分を知らず知らずのうちに追いつめてしまっていたと言ったところかな?」
恵理「優しい娘だからね」
絵夢「でも今回のことで感情も表に出るようになったし結果オーライでしょ」
恵理「だね〜」
絵夢「そういうわけであとこの『ここは夢園荘AfterStory FragmentAge』もあと2回です」
恵理「……え? そんなの初耳だよ」
絵夢「今まで言ってないもん」
恵理「おいおいおいおいおいおい」
絵夢「であであ『ここ夢FA』もうすぐ終わりですが、どうぞお楽しみに〜」
恵理「う〜〜〜〜」
絵夢「まったね〜〜〜」
恵理「う〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜」
絵夢「唸るな」
恵理「う〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜」

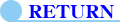
![]()
![]()