
ここは夢園荘LastStory
BEGINNING
第11話
そして運命の朝を迎える。
この日、恵理は独りでに目を覚ました。
普段なら夏樹に起こされるまで寝ているはずの彼女が、朝6時と言う早い時間に目が覚めたのだ。
恵理は広いベッドの中で、隣から聞こえてくる夏樹が朝食を作る音を聞いていた。
「大丈夫だよね……」
無意識に左手薬指の『風の指輪』に右手を重ね、その手を素肌の胸に当て鼓動を感じる。
やはり緊張しているのか鼓動が早い。
ゆっくりと上半身を起こすと、冷えた外気が素肌を刺す。
「う……ちょっと寒い……」
暖房が弱で入っているとは言え、何も身につけて無い裸の彼女には仕方ないことかも知れない。
だが、どうやらそのお陰で完全に目が覚めたようだ。
そのまま緊張を解くために両手を上下に動かしながら深呼吸をする。
同棲を始める前よりもやや大きくなった胸がその度に揺れる。
ふと深呼吸を止めると胸の下に手を当て持ち上げてみた。
「また大きくなったかな? そう言えば一緒に暮らすようになってからこっちパジャマを着たまま目を覚ましたのってどのぐらいあったかな……」
ちなみに彼女のパジャマは夏樹が以前着ていたシャツである。
思いを巡らす内に夕べのことを思いだしたのか顔が緩み始める。
そして何かを指折り数え、その度に顔を真っ赤にしては照れている。
「恵理……何やってるんだ?」
「え? あ……あははは……」
夏樹の声に我に返った恵理は布団で胸を隠しながらごまかし笑いをする。
夏樹は夏樹で少し引き気味で一緒に笑う。と言うよりもこの状況は笑うしか無いだろう。
物音に気づき疑問に思った夏樹がドアを開けると、ベッドの上で裸で身体をくねらせながら妄想モードに入っていたのだから……。
だがこれから起こることを考えればこれで良いのかも知れない。
学校へは恵理は風邪で休むと言う伝言を夏樹から由恵に託し、二人はそれぞれ準備を始めた。
準備と言っても特に用意する物もなく、恵理は動きやすく汚れても大丈夫な服を選び、それを着用した。
夏樹は102号室という物置の方から大きめの箱を持ってきた。
そこには服が入っているらしく夏樹は懐かしそうにそれを眺めると着替えた。
そして先に支度を終えリビングで待っている恵理に姿を見せた。
黒の革ジャンに皮パン、頭には赤いバンダナと言った普段の夏樹からは想像できないその様相に恵理は驚く。
「夏樹さん、その格好は……」
「現役の時に着てた服だよ。こう言うときはやっぱり決めないとな」
「はぁ……」
「変か?」
「違うの。何て言うか……いつもの夏樹さんとは違うと言うか別人って感じがして……」
そんな恵理に夏樹は微笑み、軽く唇を重ねた。
不意打ちのキスに恵理の顔はほんのりと赤くなった。
「中身は一緒だろ」
「……うん」
上目遣いで答える恵理。
まだ少し照れているようだ。
夏樹は恵理のいつまで経ってもすぐに照れてしまうところがとても愛おしく感じていた。
そして無意識のうちに彼女の頭を撫でていた。
「な、なに?」
突然の事に恵理は少しパニクった。
「いや、ただ何となく、だな」
「もう、夏樹さんはぁ」
声は少し怒っている感じだが、その表情はすごく穏やかな物だ。
二人の間に流れる穏やかな時間。
だが次の瞬間、夏樹はスッと真剣な顔つきに変わる。
そして恵理も真剣な顔へと変わった。
「行くか」
「うん」
夏樹の短い問いに恵理は力強く頷いた。
それから10数分後、二人は水瀬神社の階段下にいた。
時間は11時30分を少し回ったぐらい。
「やっぱりここなんだ」
「ああ……」
階段の上の方を見ながら短く答えると階段を上り始めた。
恵理もそれに遅れないように後をついていく。
そして一番上に着くと、そこにある鳥居の下に高志を初めとした関係者が待ちかまえていた。
「なんでここにいるのかと言うことは聞かないが……」
「夏樹が何と言おうとあたし達もついていくからね!」
澪が一歩前に出て夏樹に迫る。
だが、夏樹は冷たく「駄目だ」と一蹴した。
「なんで!」
今にも夏樹に飛びかかりそうな澪を亜沙美が羽交い締めにして必死に止める。
「ちょっと、澪落ち着いて!」
「うるさい!」
昨日の青風にやられたことを引きずっているらしくすでに切れ気味である。
「みんな、お願い!」
その言葉に、まるで最初から準備していたかのように全員で澪を押さえつける。
そして数分後……。
何事もなかったかのように高志と亜沙美が夏樹に詰め寄った。
だが夏樹は耳を貸す気は無かった。
「ついてきたところで何も出来ないし、むしろ危険だ」
「夏樹の言うことは分かるけど、私達にだって出来ることが……」
亜沙美がこの場にいる全員の気持ちを代弁する。
しかし夏樹は首を横に振るだけ。
恵理は夏樹の後ろでジッと成り行きを眺めていた。
ちなみにこのとき澪はと言うと、話がややこしくならないよう葉月達にロープで身動きを封じた上に猿ぐつわを噛まされ何も出来ない状態にあった。
う〜う〜とうるさいが、ややこしくなるよりはマシだろうと言うのが全員の統一見解。
とても仲間のやる事では無いが、どうやら昔からやっていることらしい……。
そうこうして10分近く押し問答が続いていると、突然夏樹と恵理の視界から全員の姿が消えた。
「あれ?」
恵理は突然のことにビックリして辺りをキョロキョロしている。
「心配しなくても大丈夫だよ」
「え?」
「どうやら向こうさんが気を利かせてくれたらしい」
「どういう事?」
「彼らが結界を張ってくれたと言う事さ」
夏樹は神社の裏手の林のその奥を見ながら言った。
「これが話していた結界か……みんながいないだけで何も変わらないんだね」
「そうだな」
「みんな大丈夫かな……」
「大丈夫だよ。向こうから見たら俺達が消えた風にしか見えないはずだし、それがどういう事なのかは十分分かってるはずだから」
「そっか。それなら安心だね」
「それじゃ、待たせたら悪いから行こうか」
「うん」
二人はそのまま神社の裏手へと周り、林の奥へと入っていった。
先を進むに従い、不安になってきたのか恵理は夏樹の腕にしっかりとしがみついている。
そして一番奥の開けた場所に着くと、彼らの目の前に真っ二つに切断された巨大な岩山があった。
「これは……」
さすがの夏樹もこの光景には言葉を失った。
『石』はこの岩山に開いた小さな洞窟の奥に封印されていた箱から見つけたもの。
その岩山が二つに切断され、その中央部で『石』が入っていた箱が野ざらしになっているのだ。
同時に、自分が今から相手をする者達がどれほどの力を持っているのかさらに分からなくなった。
「夏樹さん?」
わずかな表情の変化に気づいた恵理が問いかける。
「ああ……あそこに箱が見えるだろ。あの中にあったんだ」
「あの中に……」
「本当はこの二つに割れた岩山は壁みたいにこの先を塞いでいてね、その麓に小さな洞窟が開いていたんだ。
その奥にあったんだけど……」
「じゃあ、これって……」
「たぶん彼らの仕業だろうね。
しかし……この結界と言いとんでも無い『力』を持っているようだな……」
無意識の内に恵理は夏樹の腕を掴む手に力が入る。
「これでも力は押さえてるつもりなんだ」
背後から男の声。
「力を押さえてもこれか……」
夏樹は振り返ることなく答える。
「出来れば思い出の場所を壊して欲しくなかったな」
「それについては謝ろう。だがこうでもしなければ『煌玉』を取り出すことは出来なかったのでね」
「そうか……」
そう口の中でつぶやくと夏樹はゆっくりと振り返る。
それに伴い恵理も彼らを見る。
夏樹は2度目、恵理にとっては初めて会う二人−青風とエア。
「一人で来ると思っていたんだが……」
「『風の石』はこの娘が持っていてね」
「そうか……ではこちらの用件だが……」
「答えは分かってると思うけどね」
「一応、言っておきたいんだ。
君たちの持つ『風の煌玉』を貸してもらえないか」
「理由は?」
「それは言えない。恐らく言っても信じてもらえないと思うしな」
「理由も言わずにただで貸してもらおうなんて虫が良すぎないか?」
「そうかも知れない。だが、こちらとしても時間がないんだ」
「そうか……では交渉決裂だな」
「残念だ」
ここで夏樹と青風の交渉は終わった。
初めからこうなることが分かっていたのだろう、二人の顔に落胆の色はない。
「恵理、離れてろ」
「……うん」
恵理は言われるままに夏樹から離れると、岩山近くまで下がった。
その様子を見た青風もまた側にいたエアに言う。
「エア、何があっても手出し無用。いいな」
「うん、わかった」
その言葉に従うようにエアも後方へと離れる。
そして互いにパートナーが離れたことを確認すると互いを見る。
「『風の煌玉』無くして君に勝ち目があるのかな?」
「やってみなければ分からないと思うな」
「そうか……では、試させてもらう!」
瞬間、青風の姿が夏樹の視界から消えた。
「早い……だけど……」
夏樹はまるでその動きが見えているかのように視線を動かす。
「ついていけないスピードじゃない!」
青風は夏樹の左横に現れ、彼に拳を放つ。
だが夏樹は左腕でその軌道を変えると、左足を軸に右の蹴りを放つ。
青風もまたそれをバックステップで避けた。
それを初めから狙っていた夏樹はそのまま一気に間合いを詰め、青風に拳と蹴りの連続攻撃へと移った。
(思っていた以上に早いな)
青風は彼の力を過小評価していたわけではなかったが、それでも自分のスピードについてくる彼に驚きを隠せなかった。
(これは一気に片をつけた方が良いかも知れない)
夏樹の攻撃を紙一重で避けながらそう考えると、隙を狙い気をたたき込むことを決めた。
そして左から来る夏樹の蹴りをバックステップで避けると、その瞬間バランスを崩した夏樹の懐に入り込み、気を溜めた右の拳を彼に放った。
しかし、夏樹もまたその攻撃を読んでいたのかこちらは左手に気を溜め、彼の右手にたたきつけた。
「なっ!」
「くっ!」
互いに気をぶつけ合い、その反動で反対方向へと離れる。
「まさか、相殺してくるとは……正直、ここまでやるとはだがあの『力』は……」
その時、青風の目に恵理の姿が映った。
彼女は両手を胸の前で重ね、祈っているようだ。
その左手に『風の煌玉』を見つけた。
「確かに彼女が持っているのは間違いないが……」
だが彼はそれに違和感を感じた。
『煌玉』が力を使っていないにもかかわらず、青く光り輝いていた。
その輝きと目の前で肩で息をしている夏樹を見て一つの確信に至る。
「『煌玉』が離れていながら彼に力を貸しているのか。それとも……」
青風は策を変える必要があると判断した。
そして思いを巡らす青風と対峙するように立つ夏樹もまた考えていた。
(まだ左腕がしびれてるな……相殺しきれなかったと言うわけか……)
夏樹は左手を開いたり握ったりしながら無理矢理にでも感覚を取り戻そうとしていた。
(しかし……どうしたものかな……)
最初から手詰まりの自分にやや自嘲気味に笑った。
「だけど、引くわけには行かない!」
夏樹は左手をしっかりと握ると青風に対して構え直した。
そんな二人の戦いを見るそれぞれのパートナー達……。
エアは目の前の戦いが信じられなかった。
まさか青風と対等に戦う者が居ると言うことが……。
「いくら世界に影響を及ぼさない為に大半の力を封じ、その上でさらに力を押さえてるとは言ったって青風についていくなんて……」
木に手を掛けエアは、今自分に出来ることはないか思いを巡らせ始めた。
それとは対照的に恵理は手を重ね祈っていた。
決して戦いから目を逸らすことなく、ただ夏樹の無事だけを祈って……。
そして彼女たちの他にこの戦いを見つめる二人の少女達がいた。
それは『風の石』に取り込まれた楓と冬佳であった。
青風と互角にやり合う夏樹に冬佳は興奮気味だ。
「さっすが、お兄ちゃん。まけるな〜〜〜! がんばれ〜〜〜!」
冬佳はすぐにでも外に出ようとうずうずしているようだ。
そんな冬佳と対照的に楓は茫然自失の状態だった。
「そんな……」
そのつぶやきに冬佳は楓を見た。
「楓さん、どうしたの?」
「嘘です。そんなわけあるはずが……」
「ちょ、ちょっと楓さん?」
楓が自分の両肩を抱きかかえ震えだした。
「そんなわけ……無いんです……」
突然取り乱した楓に冬佳はどうしたらいいか分からず、彼女の肩を掴んだ。
「どうしたの? 一体何が?」
「あれは……あの人達は……青嵐様と空様……」
「え?」
「青嵐様は……私の師匠であり……前の代の……先代の風の守護者。
そして空様は青嵐様の補助をなさっていた方……」
楓の口から出た言葉……それは冬佳には信じられない物だった。
「だけど、それって楓さんが生きていた時の話でしょ。もう何百年も昔の話なんでしょ」
「そうです。だけど間違いありません。攻撃の仕方や体捌き……それ以上にあの人達の持つ気がそれを証明してます!」
叫ぶように言う楓に冬佳は何も言うことが出来なかった。
「もし本当だとしたら……お兄ちゃん……」
冬佳は震える楓を抱きしめたまま、互いに相手の出方をうかがう二人の姿をただジッと見つめていた。
<あとがき>
絵夢「ついに二人の正体が明らかに!」
恵理「……(^^;」
絵夢「『青嵐』と言う名前を覚えてる人がどれだけいるか……1回だけしかも名前だけですからね」
恵理「質問」
絵夢「はい、恵理君」
恵理「この空とあの空は別人ですよね」
絵夢「もちろんそうですよ。あたりまえじゃないですか」
恵理「それなら良いんだけど……ところでこの戦いどうなってしまうの?」
絵夢「ふふふふ、内緒」
恵理「う……またそれ?」
絵夢「またそれです」
絵夢「しかし、戦いの描写は辛いのぉ。ちゃんと読者に伝わるかどうか心配です」
恵理「どうだろうね」
絵夢「うむ。予定ではあと1、2回はこの調子なんで泣きが入ります」
恵理「がんばれ〜!」
絵夢「うい」
絵夢「それではまた次回も」
恵理「見てみてください」
絵夢&恵理「またね〜」

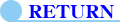
![]()
![]()